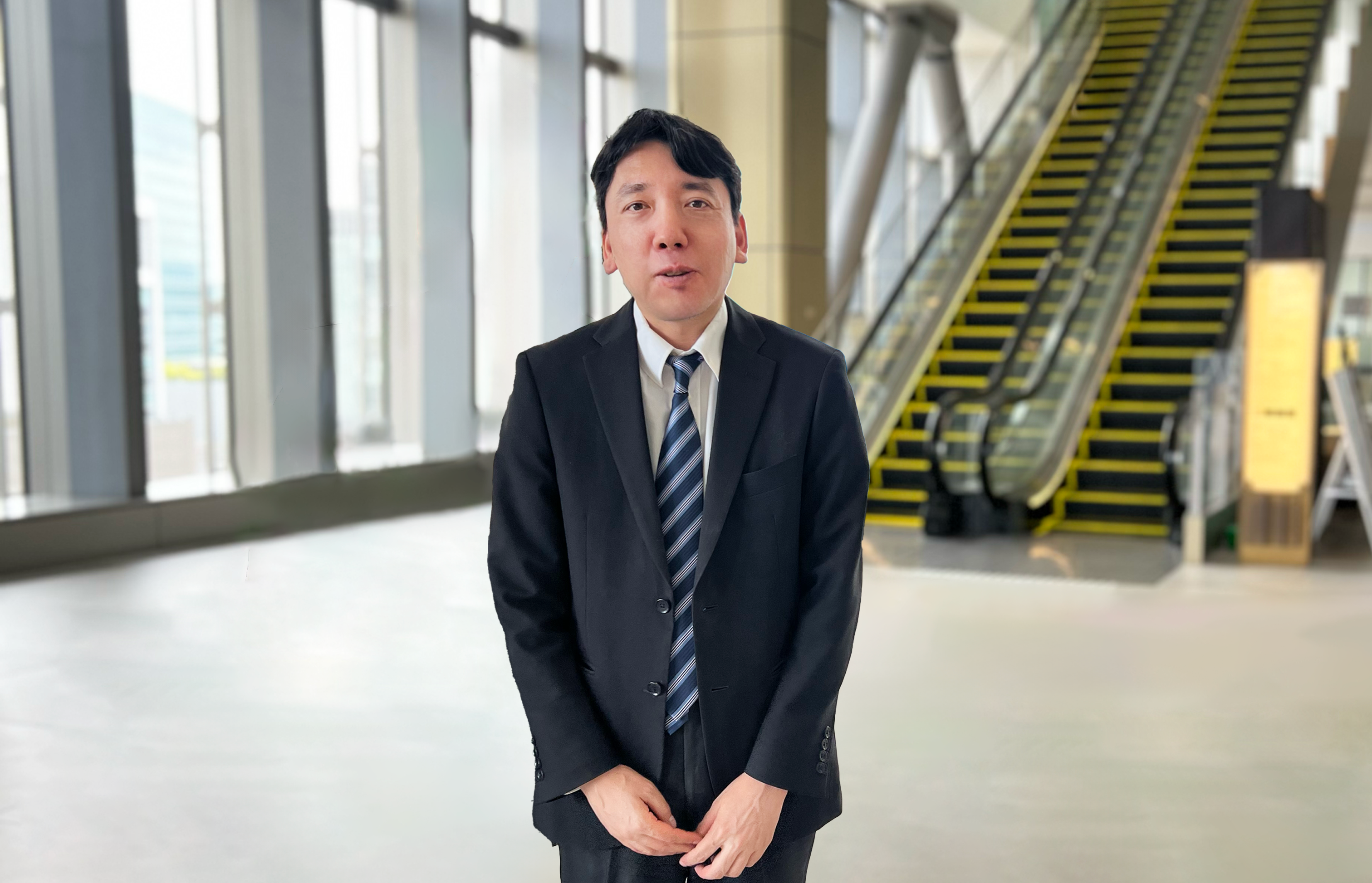
派遣社員から正社員へ。そこには、これまで様々な業界でエンジニアとして活躍してきた小林が感じた、海事産業への魅力があった。
どのような道を辿り、今に至ったのか。エンジニアとしての在り方や新たな挑戦について聞いた。
CONTENTS
- ・数学を原点とした技術者の道
- ・多彩な業界に携わり培った柔軟性
- ・BEMACとAI技術との出会い
- ・海事産業DXへの挑戦
- ・エンジニアが尊敬される社会を目指して
- ・最後に
数学を原点とした技術者の道
私のキャリアの原点は、学生時代に学んだ数学にあります。特に表現論や代数幾何といった「純粋数学」を追求し、物事を構造的かつ論理的に捉える力を養いました。一見するとこの抽象的な学問は、エンジニアとしてのキャリアに直接結びつかないように思えるかもしれません。しかし、数学で鍛えられた思考力は、後にシステム開発や課題解決の場面で「物事を本質的に捉える武器」として役立っています。
多彩な業界に携わり培った柔軟性
数学を起点にエンジニアの道に進んだ私は、卒業後、IT技術者としてアミューズメント、通信、金融、医療といった複数の業界に携わりました。業界ごとに異なる課題や特性に向き合っていく中で自然と柔軟な技術の適用力が身につき、また多角的に物事を捉える力が鍛えられました。技術者として、そこで働く人々の課題を共有し、一緒に解決策を考える姿勢は常に大切だと感じています。こうした経験が、今の私のキャリアを支えています。
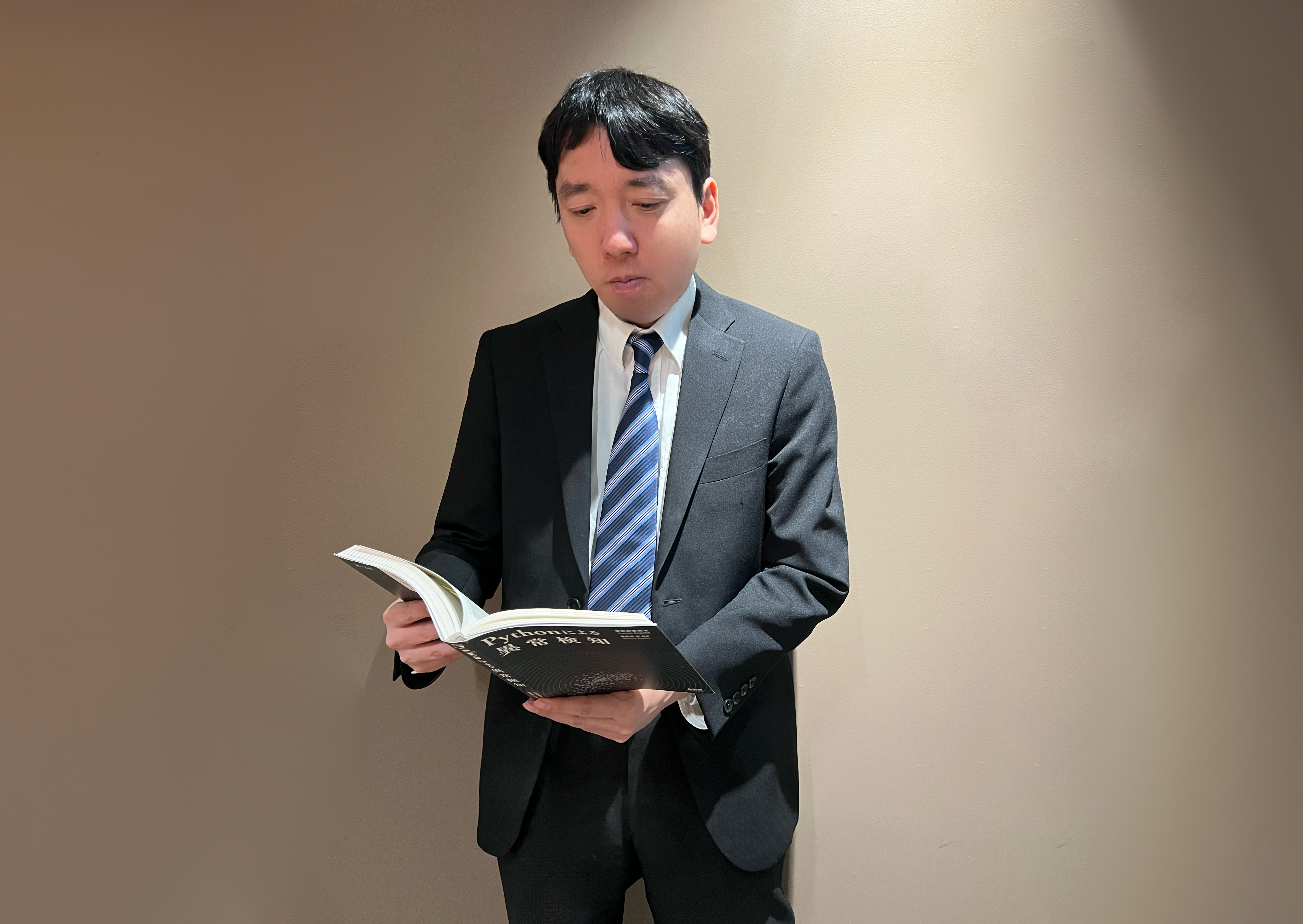
BEMACとAI技術との出会い
BEMACに正社員として入社したきっかけは、BEMACにIT派遣エンジニアとして活動していた頃に始まりました。3年間にわたって現場で仕事をするうち、会社全体に「AI技術への強い関心」があり、新しいことに挑戦する文化が根付いていることに気づきました。現場のメンバーとの信頼関係も築けた中で、「もっと深くこの会社の成長に関わりたい」という思いが芽生えました。
海事産業DXへの挑戦
現在、私は海事産業のDX推進に取り組んでいます。物流や国際貿易など重要なインフラを支えるこの産業は、長い歴史を持ち専門性が高い反面、デジタル化が遅れている部分も多くあります。例えば、AIを活用して図面検索の効率化を図るプロジェクトでは、具体的な課題が抽出され、現場の実態に即した形で進める必要がありました。こうしたプロジェクトに携わることで「技術を社会に応用する力」を日々磨いています。こうした未開拓の分野には技術者が挑むべき課題が山積しており、私にとって非常にやりがいがあるフィールドだと感じています。
エンジニアが尊敬される社会を目指して
私が目指すのは、技術を通じて社会課題を解決すること。そしてもう一つ、「技術者が尊敬される社会をつくること」です。
日本では、IT技術者の地位や評価が十分に確立されておらず、現場や経営との間に大きな溝が生じることがしばしばあります。この問題はプロジェクトの意思疎通を妨げるだけでなく、本当に必要なものが作られない原因にもなると感じています。そこで、私は技術とビジネスの間をつなぐ“橋渡し役”になることで、この溝を埋めることに挑んでいます。
子どもたちが「エンジニアになりたい」と思えるような未来をつくるには、エンジニアが誇りを持つことができる社会が必要です。そのために、まずは私自身が自分の仕事を通じてロールモデルとなるべきだと考えています。

最後に
これまで私が歩んできたキャリアは、数学で培った専門性を活用しながら、さまざまな業界で経験を重ねてきたものです。そして今、海事産業の分野で新たな挑戦をしています。技術を通じて社会をより良い方向へ変えていくことを目指しつつ、技術者としての理想的な未来を築くための努力を続けています。